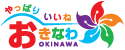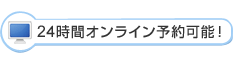オリオンツアーTOP > 沖縄ツアー・沖縄旅行 > 沖縄って?|沖縄知っとこ!

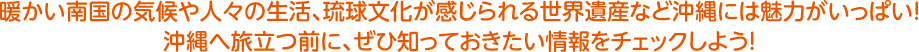





琉球王国の政治・外交・文化の中枢として栄えた国王の居城。隋所で日本と中国の建築様式を融合させた独自の芸術性を見ることができます。中心は沖縄最大の木造建築物とされる正殿。琉球建築を集めた極彩色の装飾は、当時の栄華を伺わせてくれます。その他守礼門など、琉球の歴史や文化を伝える見どころがたくさんあります。

与勝半島の根本にある四方の眺望が抜群の丘に構える城跡。阿麻和利(あまわり)が居城した城と伝えられている勝漣城跡は、沖縄の城の中でも最も古く、12世紀頃と言われています。
阿麻和利は護佐丸を滅ぼし、さらに琉球統一をめざし国王の居城である首里城を攻めましたが落城して滅びました。
小高い山の上にあるので城からの景色は最高です。

中城湾に面した高台に、北東から南西にかけてほぼ一直線に城郭が連なる城跡。15世紀中頃、築城家の名手と言われた護佐丸が築いたと伝えられています。首里王府に対抗する勝漣城主の阿麻和利を牽制するために、座喜味城主であった護佐丸が国王の命令により移り住んだ城です。しかし琉球王権を狙う勝漣城主の阿麻和利に攻められ護佐丸は自害しました。

三山時代に三山国王の居城で北山の拠城でした。背後には聖域とされるクボウ御嶽が控え、神の城として知られています。1416年に中山王の尚巴志によって三山を統一されてからは1665年まで琉球王府から派遣された監守の居城だったといわれています。地形を巧みに利用した曲線が美しいこの城壁に立てば、色鮮やかな森と海が目の前に広がります。

読谷村のほぼ中央にある座喜味城跡は、15世紀初期に築城家として名手だったと言われる護佐丸によって築かれたと伝えられています。屏風にたとえられるカーブした城壁は、その優雅さだけではなく崩れにくく敵の侵入も防ぎやすいという理に適った構造で、他のグスクでは見られない独自の様式です。

沖縄を代表する聖地で、琉球神話の源の存在であるアマミキヨが創ったと伝えられています。6つの神域があり、なかでも最高位の女性神官である聞得大君の即位式が行われた大庫理(うふぐーい)や2枚の大きな岩が重なりあって三角形の洞門を形成している三庫理(さんぐーい)は特に見逃せません。
琉球王最高の聖地として存立している斎場御嶽を訪れれば、沖縄の歴史を深く感じる事ができます。

1501年尚真王が父尚円王の遺骨を改葬するために築かれ、第二尚氏王統の陵墓となりました。墓室は三つに分かれ、中室は洗骨前の遺骸を安置する部屋で創建当初の東室は洗骨後の王と王妃、西室には、墓前の庭の玉陵碑に記されている限られた家族が葬られたそうです。左右に袖塔上には陵墓の守護神として石彫り獅子像が置かれています。玉陵を訪れれば、まるで別世界にいるような不思議な感覚を味わうことができます。

首里城の一角にある石門。木製の門扉を除き全て石造りで、八重山の名石工・西塘によって1519年に造られました。
国王が首里城を出て各地を巡る際に道中の安全を祈願した拝所です。また琉球王府の最高位の神女の聞得大君(きこえおおぎみ)が斎場御嶽で即位式をおこなう際にもここで祈願したと伝えられています。
沖縄戦で大破しましたが見事に復元されています。今でも祈願に訪れる人が後をたちません。

首里城の南に位置し別名南荘とも呼ばれる琉球王家の別邸で、池の周りを散策しながら景色の移り変わりを堪能する回遊式庭園。1800年に完成し、王家の保養所や外国からの使者を手厚くもてなす時などに使われたといわれています。
池の上に中国風に造られた六角堂があるなど、中国・日本・琉球の様式が混在した独特の風情が漂っています。
シュノーケリングを行う際、安全対策は必須です。初めてシュノーケリングを行う人はもちろん、シュノーケリングの経験がある人も油断は禁物です。楽しい思い出を作るために、正しい知識を身に付けてしっかりと準備しましょう。